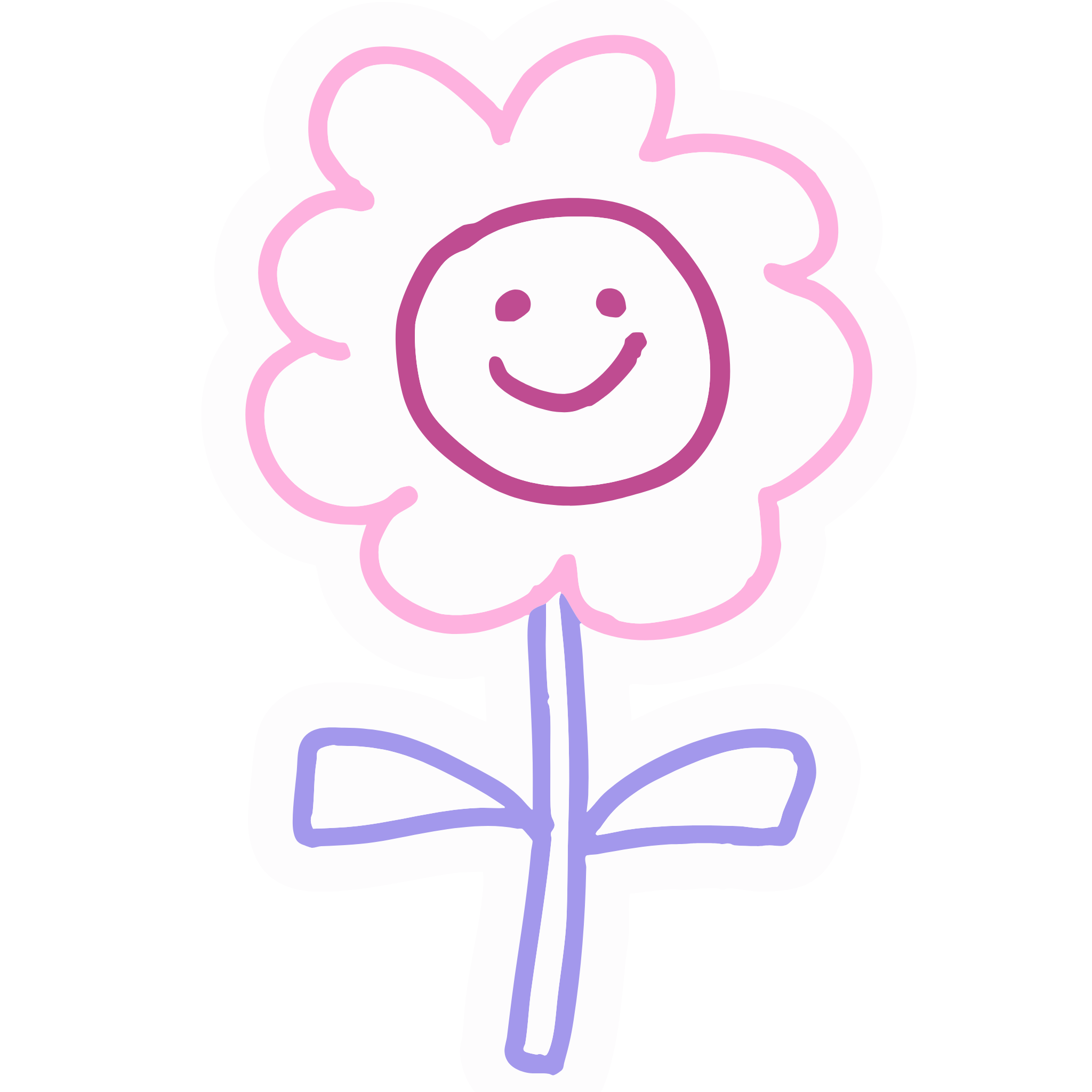「昨日は行けたのに、今日は行けない」
「頑張りたい気持ちはあるのに、身体が動かない」
そんな子どもの姿に、親の心は揺れますよね。
私の娘(小4)と息子(小2)も、まさに“五月雨登校”を経験しました。行けたり行けなかったりの波があり、親子で泣いた日もたくさんあります。
でも今は、二人とも少しずつ自分のペースを取り戻し、学校と折り合いをつけながら前に進んでいます。
そして、私自身もHSP(ひといちばい敏感な人)であり、中学・高校・大学と、同じように五月雨登校をしていました。
子どもたちの五月雨登校:それぞれのペースで過ごした1年
娘(小4)は、小学3年生の2学期から突然学校に行けなくなりました。きっかけは友達関係。心が疲れきってしまったのです。
最初はオンライン授業を自宅で受け、次第に「1時間だけ」「2時間だけ」と登校時間を少しずつ増やしていきました。そして1年かけて、ようやく教室に戻れるようになりました。(今も時々、学校内の静かな場所で過ごすこともありますが、それも彼女なりの“今のベスト”だと思っています。)
息子(小2)は、姉の不登校が始まった少しあと、小1の3学期から不安定になりました。新学期2日目には学校に入れなくなり、しばらくは登校をためらう日々。
息子は活発ですがとても優しい性格で、人を傷つけるようなことはしません。けれど小学校に入ってから、乱暴な子に出会ったり、持ち物をからかわれたり、すれ違いざまにちょっかいを出されたりと、嫌だなと感じる出来事が少しずつ重なっていったようです。
学校が安心できる場所と思えなくなったのか、次第に仲の良かった友達のことも避けるようになりました。不安が大きくなると叫んだり暴れたりして、まるで別人のようになってしまうこともありました。そんな息子の姿を見るのは本当に辛く、「どうしてあげればいいのだろう」と胸が張り裂けそうでした。
それでも姉と同じように少しずつ登校を再開し、
今では毎日休まず登校しています。
親も子も疲れ果てた「五月雨登校」の日々
正直なところ、この1年は私にとっても心身の限界を感じるほど大変でした。
朝は毎日、「今日はどうする?」から始まり、
私も一緒に授業を受けたり、教室の前で待機したり。何か月も付き添いを続けるうちに、私もどんどん疲弊していきました。
子どもたちも思うように登校できないことへのイライラから、家の中で癇癪を起こしたり、姉弟ケンカが絶えなかったり。家庭全体がピリピリしていました。
「頑張りたいのにできない」
その気持ちは、子ども自身がいちばん苦しんでいたと思います。
だからこそ、私は“焦らないこと”を意識しました。たとえその日行けなかったとしても、「また次がある」と信じて。
私自身も「五月雨登校」だった
実は、私も子どものころから学校生活が苦手でした。
中学生の頃は、親の理解が得られず、行き場を失って友達の家に逃げ込むような日々。
高校に上がるとようやく親が理解を示してくれ、送り迎えをしてくれたり、「今日は休んでもいいよ」と言ってくれるようになりました。
その支えがあったから、私は高校も大学も卒業でき、一社会人として会社に勤めることもできました。もしあのとき親の理解がなかったら、今の私はいなかったと思います。
だからこそ、今の私は、子どもたちの“行ける・行けない”に一喜一憂せず、
「この子のペースで大丈夫」と信じることを心がけています。
焦らず見守れるようになるまで ― その裏にあった苦悩
私が「焦らず見守ろう」と思えるようになるまでには、たくさんの葛藤がありました。正直に言えば、綺麗ごとなんてひとつもなかったと思います。
学校に行けない子どもを前に、どうしていいかわからず、家族で話し合ったり、時には怒鳴り合いになったりしました。「行かないならいらないよね!」と、感情のままにランドセルを外に放り出したこともあります。
優しくしたいのに、優しくできない。
付き添いの日々は、子どもよりも私の方がイライラしていたかもしれません。
「なんで私ばっかり…」
「1年生だって一人で行ってるのに」
「私は甘やかしてるのかな」
心の中は、いつも真っ暗でした。
それでも、先生方の優しい言葉や心遣いに何度も救われました。「今日はここまで頑張れましたね」と声をかけてもらえるだけで、少しだけ「これでいいのかもしれない」と思える日がありました。
子どもが学校に行けない本当の理由に気づいた日
毎日悩みながら気づいたのは、「この子は甘えているんじゃない。自分でもどうしたらいいか分からないんだ」ということ。
学校には“行きたい”という気持ちがちゃんとある。でも“安心できない”という現実がその一歩を止めている。
「ママがいたら行ける」
「ママも来て」
そう言うとき、子どもは“わがまま”を言っているんじゃなくて、「ママがそばにいないと不安で息ができない」と訴えているんですよね。
私が付き添っている間だけでも学校に滞在できるなら、それでいい。少しずつ「学校は怖くない」「ママがいなくても大丈夫」と子ども自身が感じられるようになることが、何より大切だと思いました。
もしかしたら、付き添わずに放っておいてもいつか自分で動き出したのかもしれません。でも私は不安を減らすためには「付き添った方が早い」と思い、そうしました。学校に行けていない自分へのいら立ちからか、毎日感情が不安定で荒れている子どもたちと家にいる事が難しかったことも理由の一つです。
一緒に笑えた日を、今も忘れません
付き添いの日々は本当に大変でした。
体も心も限界で、「もう無理かもしれない」と思う日もありました。
でも、ある日、学校で我が子が友達と笑って話している姿を見たとき、涙があふれました。
あの時の笑顔を見た瞬間、
「頑張ってよかった」と心から思いました。
HSCの「ゴール」は“みんなと同じ”じゃなくていい
私は今でも思います。HSCの子どもたちにとって、ゴールは「毎日、休まず学校に行けること」ではありません。
人よりも刺激を受けやすく、疲れやすい子だからこそ、「自分の限界を知り、自分でペースを整える力を身につけること。」そして、「自分にとって居心地のいい場所を選び、自分のペースで生きていく力を育てること。」それが、本当の意味での“成長”だと感じています。
学校に毎日通えるようになることは、ひとつの形かもしれません。でも、それだけが正解ではありません。
行ける日もあれば、休みたい日もある。
それでも、「自分で選べる」「自分で立て直せる」ようになることが、HSCの子どもたちにとって何よりも大切なのだと思います。
いま苦しんでいるママへ
もし今、五月雨登校の渦中で苦しんでいるママがいたら、「あなたはよく頑張っています」と伝えたいです。
焦らなくて大丈夫。
泣いてもいい。
怒ってしまっても、後悔してもいい。
それでも、あなたはちゃんと子どもを支えています。
私もそうやって、何度も転びながら進んできました。そして今、少しずつでも子どもたちは前を向いています。
“五月雨登校の終わり”は、「完全に行けるようになること」だけじゃありません。子どもが「自分のペースで進める」と思えたとき、それがひとつの“終わり”であり、“はじまり”なんだと思います。