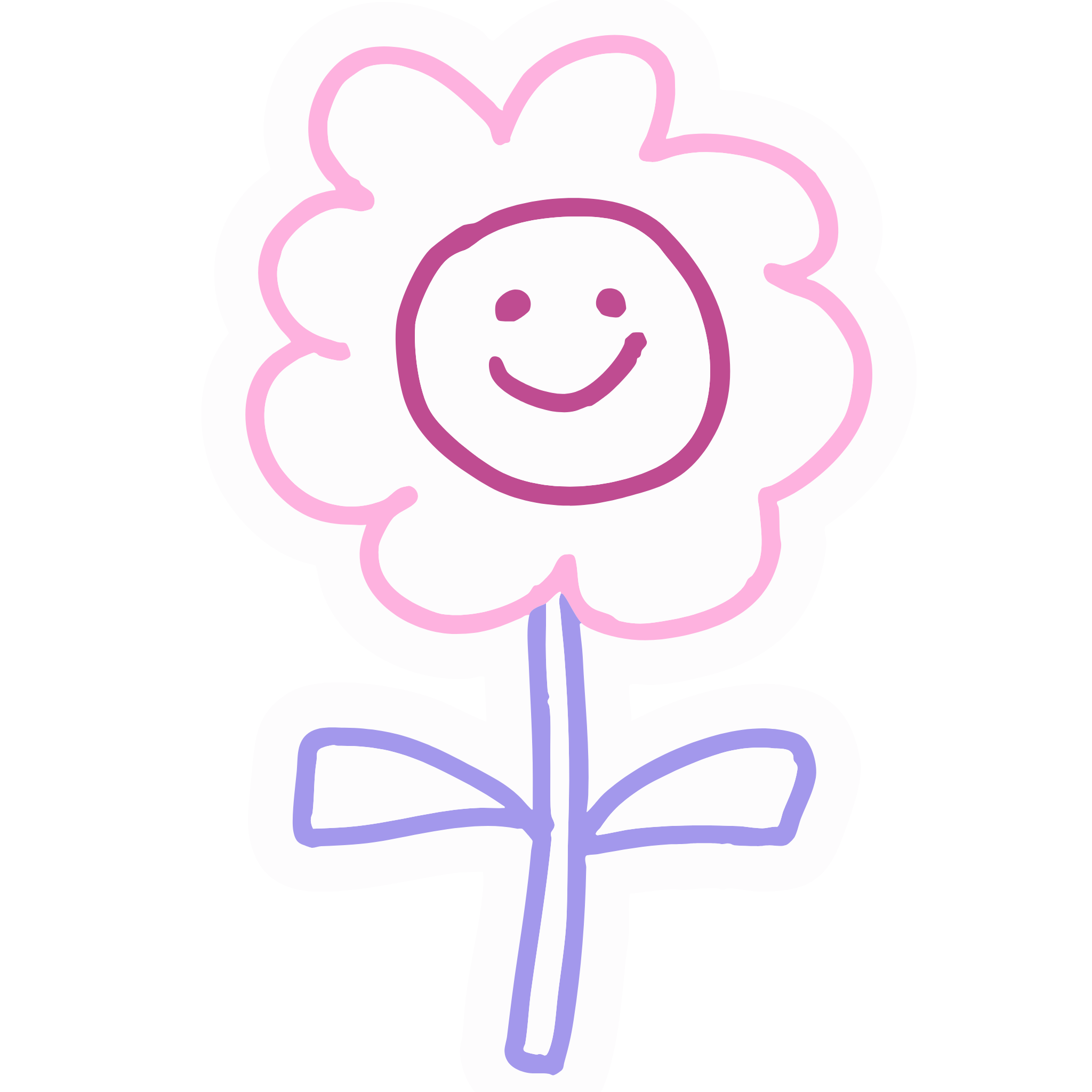HSC(ひといちばい敏感な子ども)は、環境や人間関係の変化にとても敏感です。
娘も小3の秋、友達関係のトラブルをきっかけに、どうしても登校することが難しくなってしまいました。
最初は「大丈夫、行ってごらん」と励ましていましたが、日に日に顔つきがこわばり、泣いて暴れて手が付けられない状態に…。「もうどうしたらいいの?」と、私自身が不安と焦りでいっぱいでした。
そんな経験を経て感じたのは、「不登校期には段階がある」 ということ。そして、親がその段階を理解し寄り添う必要があること。そうすれば、子どもが自分のペースで回復できる力を取り戻していくということです。
不登校には「段階」があると知る
不登校というと、「学校に行かない」状態だけを指すように思いがちですが、実はその背景にはいくつかの段階があります。
| 段階 | 子どもの様子 | 親の関わり方のポイント |
|---|---|---|
| ①行き渋り期 | 体調不良を訴えたり、欠席遅刻早退や、保健室にいることが増える。 | 「どうしたの?」より「何か疲れてる?」など体調ベースで話す。「休んでもいい」と伝える。 |
| ②混乱期 | 学校に行けなくなった自分に戸惑う時期。学校の話をしたがらなくなり、昼夜逆転生活になることも。 | 「今は休む時期」と割り切り、安心できる環境を整える。まずは、心の回復を優先する。 |
| ③安定期(慢性期) | 行かないことが当たり前になり、落ち着いて過ごすようになる。笑顔で過ごす時間が増えてくる。 | 短い外出などから始め、少しずつ外の世界との関わりを取り戻す。焦らず見守る。 |
| ④回復期 | 「暇だな」「○○なら行けるかも」「先生に会いたい」など前向きな言葉がでてくる。 | 学校と連携を取り、できることからやってみる。焦らずサポートする。 |
この4つの時期を行ったり来たりしながら不登校から復帰していきます。
私の娘は正にこの通りで、①の時期は登校しぶりや体調不良・保健室登校が増え、お迎え要請の電話が毎日のように鳴りました。②の時期は、”行かなきゃいけないのに行けない”自分に混乱し、些細なことで泣いたり怒ったり、情緒が不安定でした。ずっと寝ていて起こしても起きません。③の時期には笑顔が出始め、一緒にカフェに行くことも。④の時期には、オンラインで授業を受けてみようかな…と実際に受け、友達の名前を呼ぶ姿が見られました。そこからは、スモールステップでできる事を増やして自身を取り戻していきましたが、できた!と思ったことがまたできなくなったり、学校に行けた!と思ってもその後何日か休んだり、不登校は振り子のようでした。”一歩進んで二歩下がる”ことも多々ありますが、決して振り出しに戻ったのではなく、戸惑いながらも着実に成長しています。焦らず・子どもの事も自分の事も責めず、親子で協力して乗り越えていくことが大切です。
我が家の体験談はこちらです↓


HSCの子は「安心感」が行動の鍵
HSCの子は、人の気持ちや空気を深く感じ取る分、
少しのトラブルや言葉でも大きなストレスになります。
娘の場合も、友達との小さな誤解がきっかけで、
「また同じことが起きるかも…」という不安が大きくなり、
学校そのものが怖い場所に感じてしまいました。
息子の場合は、乱暴な子とトラブルになり、同じクラスになってしまったことがきっかけでした。
どちらのケースにも共通していたのは、「学校=安心できない場所」になってしまった ことです。
不登校の子が再び動き出すためには、
「安心して大丈夫」と心から感じられることが最初の一歩になります。
親ができる4つのサポートステップ
① 否定しないで受け止める
「行けない」=「怠けている」ではありません。
「そう感じるんだね」と気持ちを受け止めることが、子どもの心を守ります。
②安心できる家庭の空気をつくる
学校に行かないことで家庭がピリピリすると、
子どもはますます「自分が悪い」と感じてしまいます。
笑顔を作れない日があっても大丈夫。「ここにいていい」と伝えるだけで充分です。
③ 少しの変化を見逃さない
たとえば「先生の話を聞こうかな」「今日は玄関まで行けた」など、
ほんの小さな前進を見つけて、言葉にしてあげましょう。
④ 親自身も支えをもらう
不登校期は、親も心がすり減ります。
学校やスクールカウンセラーに相談したり、同じ経験をした親の声を聞くことも大切です。
焦らなくて大丈夫。子どもは自分のペースで育つ
娘もまったく登校できない時期がありましたが、
「学校が怖い」「泣いてしまう」という気持ちを受け止めるうちに、
少しずつ自分の気持ちを話せるようになっていきました。
ある朝、「ママと一緒なら行けるかも」と言ったその言葉が、
我が家の再スタートでした。
焦る気持ちは誰にでもあります。
でも、子どもが自分で「行ってみようかな」と思える瞬間は、
親がどれだけ心を寄せて待てたかの先にあります。
まとめ
不登校は“止まっているように見えますが、その子にとって必要な成長の時間”。
焦らず、見守りながら、子どもが自分のペースで前に進む力を信じていきましょう。