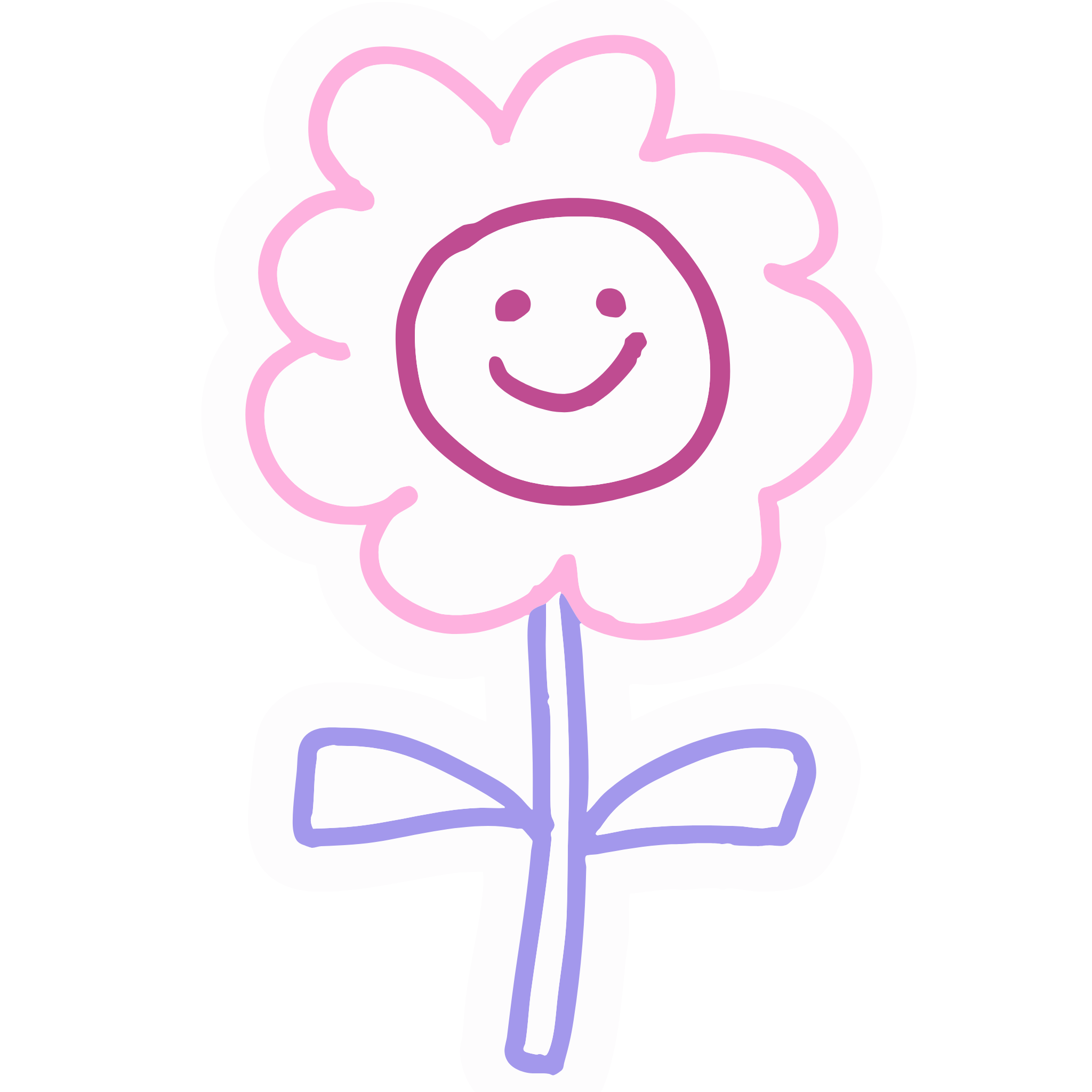HSC(ひといちばい敏感な子)にとって、学校は刺激の多い場所。ほんの少しの環境変化や人間関係のストレスが、心と体のバランスを崩すきっかけになります。
我が家では、娘と息子の“行き渋り期”をそれぞれ経験しました。どちらも、最初は体調不良や癇癪など「よくある変化」に見えて、まさか不登校につながるとは思っていませんでした。
でも今振り返ると、あの時こそが「心のSOS」だったのだと気づきます。
娘(小4)の場合:笑顔の裏で無理をしていた「がんばり屋のサイン」
娘は小3でクラス替えをし、仲の良い友達と離れました。それでも放課後は新しい友達と楽しそうに遊んでいたので、すっかり安心していたのです。
けれど、次第に朝起きてこなくなり、「お腹が痛い」「気持ち悪い」と体調不良を訴えることが増え、保健室にいる日が多くなりました。微熱で早退したり、家ではイライラして癇癪を起こしたり、蕁麻疹が出ることもありました。
きっと本人は気づかないうちに無理をしていたのだと思います。
後になって話してくれたのは、
「隣の子に筆箱を取られる」
「突然怒鳴る子がいて怖い」
「女子同士のケンカが多くて落ち着かない」
といった、日常的な“怖さ”や“疲れ”でした。
仲良くなった子たちと違う係になったことで孤立感も感じていたようです。
周りに合わせて頑張っていたけれど、心は限界に近づいていたのかもしれません。
息子(小2)の場合:「楽しい」よりも「不安」が大きくなった時期
息子は小1の3学期ごろから「行きたくない」「やりたくない」と言うようになりました。話を聞くと、学校での嫌な出来事の方が多くなっていました。
イベントでダンス係を勧められて引き受けたものの、本当はやりたくなかった。その他にも小さな嫌な事があることをたくさん話してくれました。3月には原因不明の発熱を繰り返し、3週間ほど登校できない時期もありました。
朝はギリギリまで着替えず、車で送ってもおりられない。同じ時期から習い事も行き渋り、車からおりられず泣いていました。
ある日の朝、仲の良いママさんから
「〇〇くん、一人で帰るって外にいるよ!」と電話があり駆けつけると、遅刻ぎりぎりで送ったはずの息子がそこにいました。「教室の前までは行ったけど入れなかった…」と。
この頃から、嫌な事があると泣いたり暴れたり情緒が不安定になっていきました。
息子はまだ自分の気持ちをうまく言葉にすることができず、態度で示すことで一生懸命伝えようとしていたのだと思います。
2人の行き渋りが重なった時期
2学期に姉が登校できなくなり、少し気持ちが落ち着いた3学期から今度は息子が渋り始めました。
とにかく毎日学校まで連れていくことに必死でした。
道中もケンカが始まり「もう行かない!」と大泣きしたり、学校についても中に入れずかたまってしまったり、下の子の送りもあるのに「ママもずっといて!」としがみついて離れなかったり、やっと送り出しても早退の電話が鳴ったり。
なんでこんなにストレスに弱いんだろう…
私の育て方が良くなかったのかなと自分を責める毎日でした。
家でも子ども達は一日中ピリピリしていてケンカばかり。そして私もどうしたら良いのか分からない不安や疲れからピリピリしてしまっていました。
それぞれとゆっくり話す時間も取れない毎日。本当に辛かったです。
結局、新学期も2人とも不安定なまま。息子は始業式の初日だけ登校し、その後は行けなくなってしまいました。
この時期を振り返ると、「無理に行かせるよりも、早めに休ませて話を聞くべきだった」と思います。担任の先生とも情報を共有しながら、不安の根っこを一緒に探す時間を持てたら良かった。
当時の私は、たくさん話を聞いていたつもりでしたが、そのあとに「みんな頑張ってるよ」「熱もないんだから行けるよ」と励まし、結果的に“寄り添ったつもり”で“突き放して”いました。
行き渋り期のお母さんへ伝えたいこと
この時期のお母さんたちはきっと、
「休み癖がつくのでは…」
「仕事もあるし休ませていいの?」
「熱もないのに?」
と悩んでいると思います。
でももし体調不良が続いたり、強い行き渋りが出てきたら、一度立ち止まって休ませてあげてください。
そして、たくさん話を聞いてあげてください。
ポイントは“アドバイスをしないこと”。
「どうしたらいいの?」と答えを求めるよりも、
「どうしたいと思ってる?」「どんなときに安心できそう?」と、本人の気持ちを丁寧に聞いてあげてほしいのです。
もし本人も自分の気持ちが分からない様子なら、
「どうしたら不安が少なくなるかな?」
「一緒に考えてみようか」と寄り添う姿勢で話してみてください。
最後に
行き渋り期は、心と体が「助けて」と言っているサイン。
学校に行く・行かないよりも大切なのは、
子どもが安心できる時間を取り戻すこと です。
焦らず、比べず、子どものペースを見守ること。
それが、HSCの子どもたちにとっていちばんの支えになると、今は心から感じています。