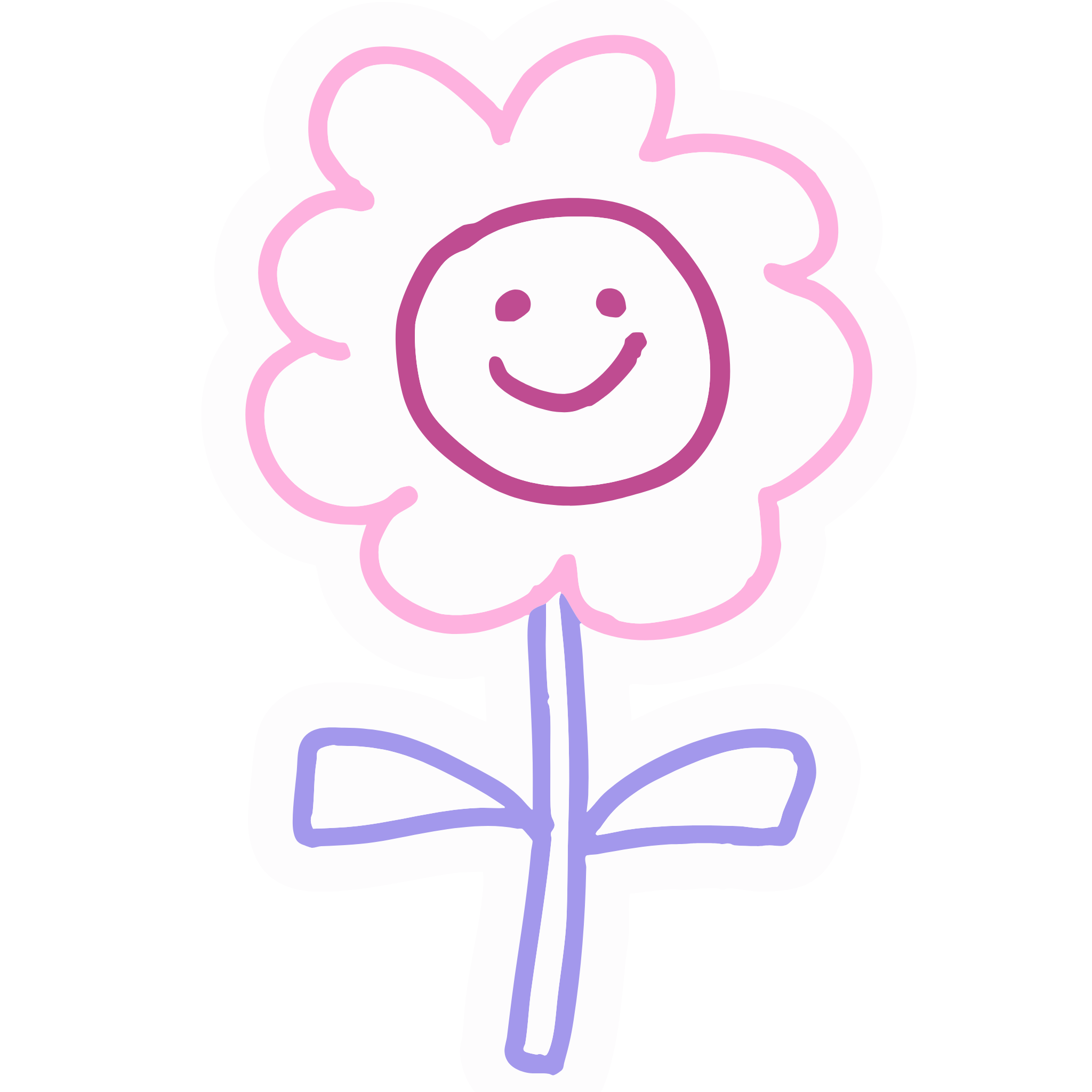行き渋り期を経て、子どもたちは「混乱期」に入りました。
学校に行けなくなった自分に戸惑い、どうしたらいいのか分からなくなる時期です。
学校の話をしたがらなくなり、感情の波が大きくなったり、昼夜逆転になることも。
親としては「どうしたらいいの?」と焦るばかりの時期かと思います。私もそうでした。
娘(小3)が見せた“心の限界”と「休みたい」の言葉
娘はよく自分から「休みたい」と言っていました。それでも私が説得し、1時間目だけだったり3時間目からだったり、自宅でタブレットを使ってオンラインで授業を受けたり、少しでも学校から離れないよう毎日なんとかやり過ごしていました。
しかしある日、いつものように1時間だけでもと学校へ連れて行ったら、正面玄関で泣き出し、動けなくなりました。30分程落ち着くのを待ちましたが中に入ることはできずに帰宅。それまでずっと頑張ってきたけど、とっくに限界だったのだと思います。
「行きたいけど行きたくない。」
次の日も学校に入ることができませんでした。ここまでも遅刻・早退でなんとかやってきましたが、ついに入れなくなってしまった娘に正直戸惑いましたし、私自身が不安でいっぱいでした。
小学生は学校に行くものなのに、行かない入れない。どうしたら良いのだろう。とりあえず「ここまでこれただけでも頑張ったよ!」と本に書いてある通りの言葉をかけたような記憶があります。
混乱期は“心を休める時間”でいい
娘の「休みたい」の言葉を無視した結果こうなったんだなと思いました。だから次の日からは娘の言う通り学校を休ませました。
混乱期の間、私は勉強や登校を一切求めませんでした。代わりに「好きなことをしていいよ」と伝え、自然に起きるまで寝かせ、YouTubeもゲームもOKにしました。
スマホの充電に例え、「あなたは今充電が0%なの。少し充電しても10%20%じゃすぐにまた電池切れになるでしょ?今は100%になるまで充電が必要だから、ゆっくり休んで充電がたまったら教えてね。充電がたまったらまた動けるようになるから大丈夫だよ。」と伝えました。
学校からは、関わりをなくさないよう「宿題だけでも出しに来ないか」と言われましたが、本人が嫌がったので、この時期はすべてお休みしました。
ちょうど冬休みに入ったことで、さらにゆっくり過ごすことができました。罪悪感もなく穏やかに過ごせた期間でした。
そして年明け、娘が言いました。
「私、もう十分休んだから3学期から頑張ろうと思ってる。」
私はその言葉に胸がいっぱいになりました。
「休む時間は、ママにとってもあなたにとっても必要な期間だったと思うよ。」
そう伝えると、娘は静かに頷きました。
私自身、過去に心が限界を迎えたことがありました。何もできず、ふがいなさと自己嫌悪でいっぱいになった時期でした。
だからこそ、娘の「行けない」には理由があると感じました。
心に余裕がなければ、人は頑張ることはできないのです。
息子(小2)が抱えた“分からない気持ち”
小2の息子は娘とは違い、自分の気持ちを言葉にできませんでした。小1の3学期から行き渋りが始まりましたが、仲の良い友達もいたのでなんとか登校していました。それでも放課後は毎日のように友達と遊んでいたのに一切遊ばなくなり、「疲れた」とよく言うようになりました。朝の準備をせず不機嫌になってぎりぎりで登校することが多かったです。
2年生になった新学期、初日も不安そうにしていましたがなんとか登校しました。しかし、2日目には校舎内に入ることができませんでした。クラス替えなどもあり不安でいっぱいだったのだと思います。
「休む?」と聞いても「やだ!」、「一緒に行こう」と言っても「やだ!」。でも「休みたい」や「行きたくない」とは一度も言いませんでした。その様子に気づいた先生が声をかけてくれましたが、息子は目を合わせず一言も話しません。「今日は無理そうなので帰りましょうか」と声をかけていただき、この日は帰宅しました。
この頃から、ストレスから発熱することが増え、癇癪もひどくなりました。私は娘のときと同じように、「とにかく休ませよう」と決めました。
息子はゲームが好きなので、マインクラフトや釣りゲームなど好きなものを自由にさせました。
普段ならゲームやYouTubeなどのメディアは1日1時間と決めていましたが、この時期は時間制限もせず、ただし「1時間に1回は目を休めようね」「ごはんやお風呂の時間はやめようね」と、ゆるやかに声をかけました。
それだけで、少しずつ心が落ち着いていったように感じます。
限界を感じ、初めて“支援を頼む”と決めた日
この時期は、五月雨登校の送り迎えや付き添いが必要な娘と、学校に行けなくなってしまった息子を見守る中で、私自身もどんどん疲れていきました。「これ以上どうしたらいいか分からない…」そんなとき、私はChatGPTに相談してみました。
返ってきた言葉は、
「その状況は家庭支援が必要です。お母さんひとりでは無理です。」
無理か。確かにそうだよね。私もそう思っていたけど、(体が足りない、私がもう一人…いや、もう2人くらいいたら良いのに)と思っていたけど、夫は仕事があるし実家は遠方だし、一人で頑張るしか選択肢が無いと思っていました。無理だとはうすうす気づいていたけど、母親であることの責任から、頑張るしかないんだと頑張っていました。私ももう限界が近かったと思います。
はっきり無理だと言ってもらえたことで、肩の力がふっと抜けました。“ひとりで抱えなくてもいい”と気づいた瞬間でした。
担任との面談で見えた、息子の“本当の気持ち”
それをきっかけに、初めて担任の先生に面談を申し込みました。「学校に信頼できる大人がいないことが、行けない理由の一つなのかもしれない」と感じたのです。
ところが当日、息子は校門前で立ち止まりました。「やっぱりムリ。誰にも会いたくない!」
それでもなんとか中へ入ると、友達を避けるように走って逃げてしまいました。
面談中も落ち着かず、先生の目を見ようとしません。質問されても答えません。見ていてつらい気持ちになりましたが、後から息子が言いました。
「先生にがっかりされたくなかったんだ。」
その言葉に、私はハッとしました。
頑張れない自分を恥ずかしいと思っていたのです。
面談が終わったあと、息子は小さな声で言いました。「でも、今日行けて先生と話せて少し安心した。」
先生も理解のある方で、「まずは朝だけ来て宿題を出すところから始めてみようか」と提案してくださいました。
私が同じことを提案するよりも、担任の先生から「大丈夫だよ。自分のペースでいいんだよ。」と直接言ってもらう事が大事なんだなと感じました。息子は頷き、そこから少しずつ前を向くようになりました。
まとめ:休むことは、立ち止まることじゃない
混乱期は、子どもの心が整理されていく大切な時期です。「行けない自分」を責めず、「休む勇気」を持てたことこそが、次への一歩。
無理に登校させなくても、焦らなくても大丈夫。
子どもも親も、それぞれのペースで少しずつ回復していけばいいのです。
そして、もしお母さん自身が限界を感じたら、「助けて」と言っていい。支援を頼ることは、弱さではなく、愛情のかたちだと私は思います。